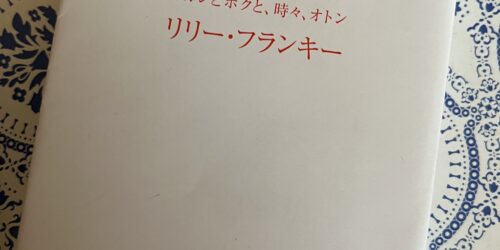「東京タワー」読了
先日、ふと「読書メーター」(自分の読書記録をつけるサイト)に今年読んだ本を書きました。
読書メーターの感想文は255文字やったかな?その範囲で納める仕様になってます。
255文字で書けないこともないけど、大概は短こぉて書きたいことが書ききれません。
なんやせっかく読んだんやし、ちゃんと残るような感想文を書こうかなと思ったら、今回思いのほか長くなりました(笑)
それでも書ききらず・・・というか、1つの文章で書ききると書きたいことがチグハグになってしまうので前編・後編に分けてみよかと。
といっても、前編は~ピリッと編~っていう態(てい)で普通の文章で綴る感想文。
後編は~ゆるっと編~で、本音というか感じたままを口語体で書いてみる感想文。
これから読んだ本は感想文にして残していこかなぁと思てますが、ピリッと編とゆるっと編の同時を書くかどうかは未定。
どちらか一つだけかも知れんし、どっちも書くかも知れへんし。
まぁ、そんな感じでせっかく読んだ本を何度か楽しめたらなぁというのと、興味もってもらえたらなぁという思いで書いてみます。
いずれにしても長文ですが、興味があったら、読んでみてください(笑)
東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~
リリー・フランキー著/新潮社
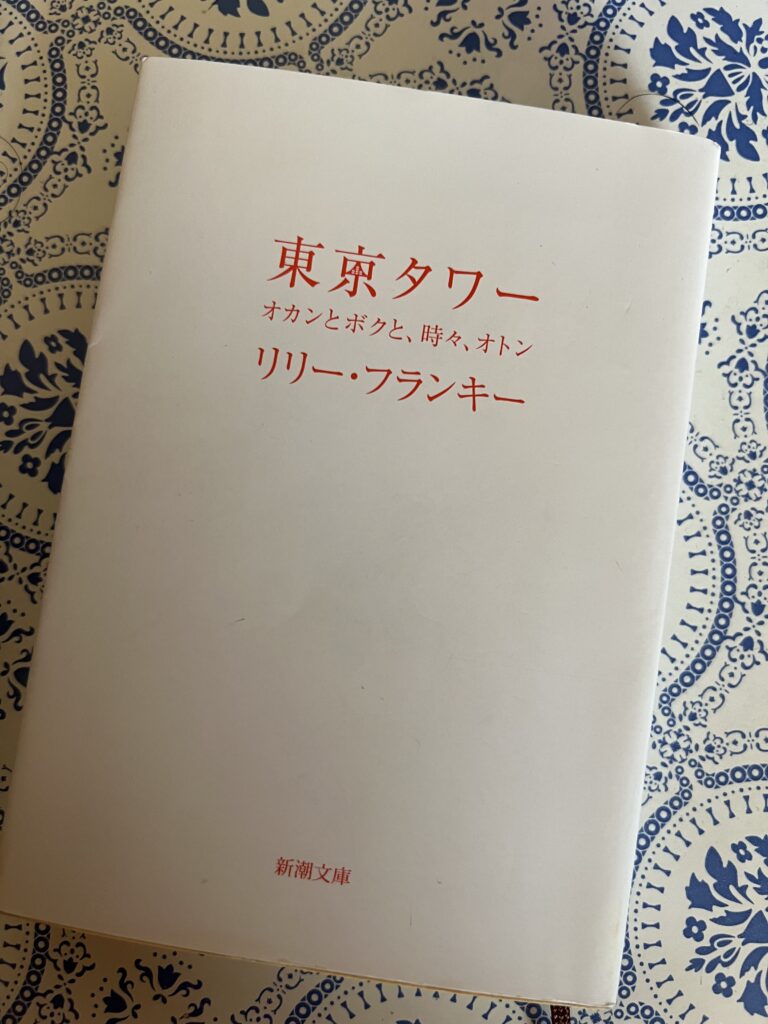
感想前編【ピリッと編】
「母子家庭」
それが作者と私の共通点だった。といっても作者の両親は離婚しないままの母子家庭だったので私とは少し違っていた。
ただ昭和時代の母子家庭特有の世間との乖離や周りからの刷り込み、世の中のどこにも馴染み切れない感情などは多く共感した。
このお話は、作者のあるがままの表現で作者の一番古い思い出から母親が亡くなるまでの間の思い出を丁寧になぞって描かれている。
主に母親を主体にしているが、親と子のつながり、家族のつながり、また夫婦のつながりも違和感なく、しなやかに紡いでいる。
また文章(本)にするからと恰好をつけるということもなく、素のままの洗いざらいな状態で作者自身の至らないところも、家族の普通の家族らしからぬ点も包み隠さずに描かれている。
作者の成長と共に、家族の延長線上にあたる接点の少ない親族の老いの例えから、両親に至る老いへの表現などは客観的かつ第三者の目線で、冷酷にリアルに表現されている。
そんな節々が心をギューッと切なくさせた。
特異な家庭環境で育った作者が「家族とは」という問いは、図らずも私の死んだ父親が酔いつぶれて私に問いかけた永遠の解けない謎を一つ垣間見せてくれたような気もした。
作者は独身者で子供もいないようだが、親の愛、特に母親の愛というものを強く感じ、理解しているように思える場面があった。
それはこの一場面。
作者の母親が死期も近づき、食べ物もほとんど喉が通らなくなっているのに、病院食に出てきた母親自身も好物であるプリンを残し、同じくプリンが好物な(とっくに成人しきった成人男性たる)作者に「(アンタ好きでしょ)食べなさい」といって与える場面だ。
もう何も食べることができなくて、わが命が燃え尽きようとしているその寸前ですら、自分のことよりも子供の好物を子供に与える本能的な母親の愛がその一文に凝縮されていた。
この描写に
「あぁ。せやなぁ。オカンって、こういう生き物や」
と、どんな場面よりしみじみと心から涙が溢れた。
子供がいない私に「子を想う親の気持ちは分からん」と言われることがある。
確かにそうかも知れない。でも、子供がいないなりにも実際こうして親心をくみ取ることができる事実もある。
文中で
”歌手や宇宙飛行士になれなくても、いつか自分は誰かの「お母さん」や「お父さん」にはなるんだろうなぁと思っている。しかし、当たり前になれると思っていたその「当たり前」が、自分にはおこらないことがある。
…中略
叶っていいはずの、日常の中にある慎ましい夢。子供の時は、平凡を毛嫌いしたが、平凡になりうるための大人の夢。かつて当たり前だったことが当たり前ではなくなった時。平凡に躓いた時。人は手を合わせて、祈るのだろう”
という文章を読んだとき、少なからずも作者は「平凡と呼ぶ普通の家庭」も夢に見てはいたんだろうなぁと、強く共鳴した。少なからず、私もそうであったからだ。
そして子がいない故に親の心を分かり得ない私のように、また「子を持てなかった人の気持ち」は、子供を待つ人には分からないと強く思った。
しかし、そんな気持ちは共感しあえないことが良いのは分かっているし、言われた相手に言い返すつもりもない。
ただ年を重ねるごと人が思う以上に、わが子(直結する血のつながり)がいないからこそ、強く、必要以上にとても強く、親を想う気持ちがあるのは、世の中の誰かに少しくらい理解してもらえたらなぁと思うことはある。
特に母子家庭の子供にとって母親は、母親でもあり父親でもある。両方を持ち合わしたその存在感たるや単純に2倍とはいかないのだから、親への想いたるは他人が思う以上に強いのである。
それが故、物語の中で作者が一番恐れるものは、寸分たがわず私も一番恐ろしく思っていて、いまだその恐怖におののいている。
しかし、あえて今はその話題はしない。作者が恐れたように、私もまた今なお何よりも恐ろしくて、語りたくないのだから。
このお話では、父親が「時々」という割に大きな存在として節目節目に登場している。
世の中で言う「父親らしい父親」ではないかも知れないが、私からすれば案外父親らしく、それも子を想うよい父親だった。
ただその愛情表現が一般的でないだけのこと。
父親と母親の不思議な夫婦関係もまた魅力的に描かれている。
きっと父親も母親も互いに恋しているけれど、最後まで愛し方が分からないままだったのかも知れない。
作品中、”ボクの父親と母親が本当の夫婦なのだなと思える記憶に少ない情景”という何気ない場面に出会えたのは、作者にとって幸せなことだろう。
私には生憎、両親が本当の夫婦なのだなと思える場面もなければ、家族水入らずで楽しく過ごした記憶もない。
それだけに母親の死に際、病室で作者と母親、父親3人で手を取り合って安らかに眠りについて病室ではないどこかに3人で出かけた思い出は私にとって羨望以外の何物でもなかった。
文頭に書いた私の父からの永遠の課題「家族とは」を作者はこう綴っている。
”たった1度、数秒の射精で親子関係は未来永劫に約束されるが、「家族」とは生活という息苦しい土壌の上で、時間を掛け、努力を重ね、時には自らを滅して培うものである”
それを「親としての自覚」や「男女としての自覚」はたまた「一個人としての自覚」をもって接していくものだと。
そして”どれだけ仕事で成功するよりも、ちゃんとした家庭を持って、家族を幸せにすることの方が数段難しいのだ”と。
言い得て妙だが、まさしくその通りだなぁと感心した。
ただ、それが私にとっての「家族とは」という問いの答えになるかというと、それがすべての答えではない気がした。
「家族とは」
その真意をいつか私が理解できるのだろうか?
その答えにいつか私はたどり着けるだろうか?
そんなことを考えさせれる一冊だった。