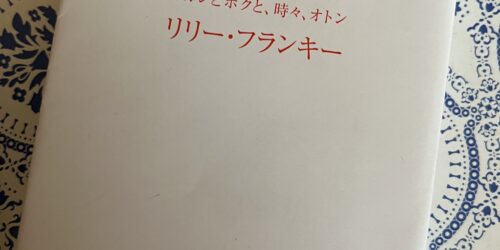「東京タワー」読了②
さてさて、前編・後編に分けてみよかと書いた読書感想文です。
本音というか感じたままを口語体で書いてみる「後編~ゆるっと編~」
興味があったら、また読んでみてください♪
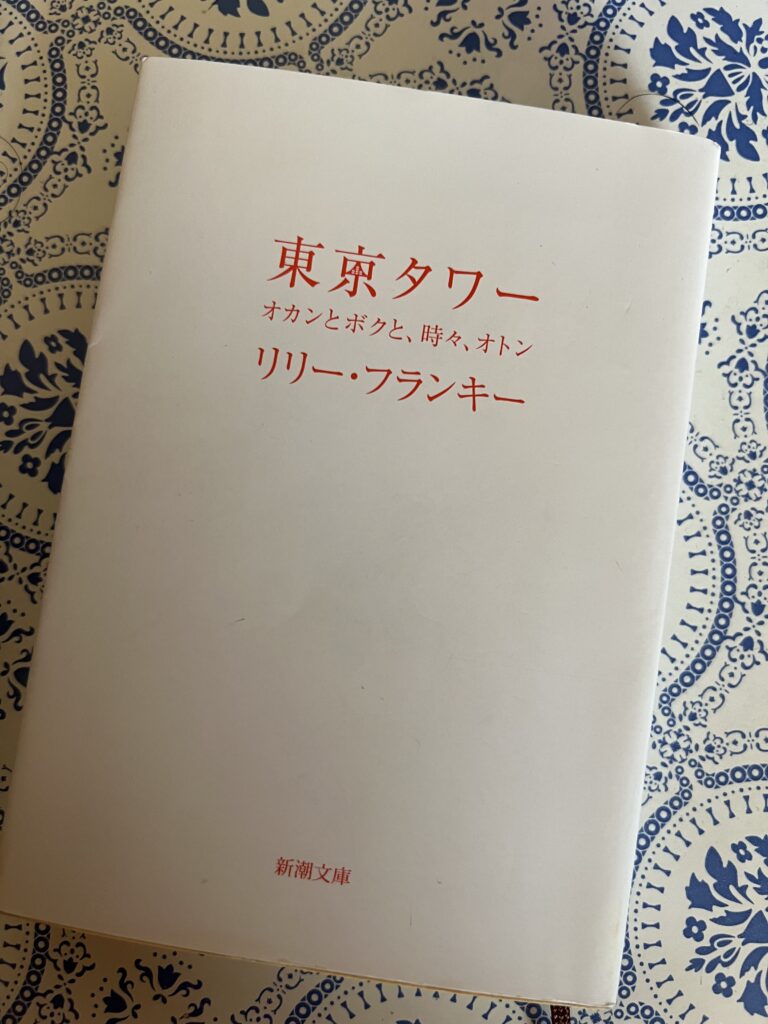
東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~
リリー・フランキー著/新潮社
感想後編【ゆるっと編】
映画にもなったというこの作品は、よくある「郷愁を漂わせつつ、親との絆を涙でつづる感動の作品」という風な感じなんやろなぁと思って読み始めました。
気になっていたと言え、今まで読んでなかったのはそんな理由。どっちかて言うとお涙頂戴、感動の名作といった謳い文句のメジャー級の本や映画は苦手なもんで。
せやけど、今回はちょっとした目的もあって「読んでみよかな」と手に取ってみたんです。
最初のエピソードは、なんやドラマチックに書き始めてる感じもしたけど、そのうちサラリと物語に飲み込まれていきました。
そもそも飲み込まれた理由が、作者の特異な家庭環境でした。
母子家庭(作者の両親は最後まで離婚されてないけれど)、離れて暮らす父や親戚とのやり取りが、なんや自分によぉ似てたからです。
とは言え、同じ母子家庭やけど、そこはやはり家庭の違い。性別の違い、兄弟のあるなしの違いでウチとは大きく違ってました。
恐らく貧乏なんやろけれど、ホンマに一銭もない貧乏やのぉて、貧乏なお坊ちゃんという感じで育てられてはりました。
だから「同じ母子家庭でも物にも人にも恵まれた幼少期を送ってはるなぁ」と読みながら羨ましなってました。
ウチは・・・ウチの母と私は少なくともホンマにお金にも人にも恵まれんかったので、母のその苦労たるや、こんな美しい話には仕立て上げられませんから(笑)
母がどれだけ人というもの(親・兄弟とは言え、自分以外の人間)とお金で苦労させられたか目の当たりにしてきたので、私は人に対して懐疑的やし、お金に対してもドライになってしまいました。
だから、この作品のようにちょっと切なくてホンワリ優しい気持ちの世界が「本の中の世界」として見えてしまうのも正直なところ、ありました。
ただ母子家庭の子供として共感する部分は多々あって、特に父親と母親がぎくしゃくしてる時の子供の目線なんかもそうです。
うまくいってない夫婦(家族)の中で育つ子供の目線を表した一文です。
“淋しいのではなく、悲しいのでもない。それはとてつもなく冷めた眼で見ている。言葉にする能力を持たないだけで、子供はその状況や空気を正確に読み取る感覚に長けている。そして、自分がこれから、どう振る舞うべきかという演技力も持っている。
それは、弱い生き物が身を守るために備えている本能だ”
夫婦は所詮他人でも、子供にとってはそれぞれが血のつながった自分の親なんですよねぇ。
それが故に、どんな母親や父親であっても心のどこかで「うまくいっててほしい」とは望むものです。
でもそれがそういかないとき。
なんとか自分が居ることで、その関係をスムーズにできたなら・・・いや、せめてその場を温和にできたなら・・・と子供ながらに思うんです。
当然、そんなことうまくできるはずはないんですけど。
そして作者が長い休みごとに、父親の元に行き来する気持ちもすごく共感しました。
日頃、一緒に過ごしていないから「家族感」というのは実のところとても薄くて、話すこともそないにないし、そのうち会話は少なくなって、ただただその期間だけお互いがその場に「居てる」だけの日々を過ごします。
「ただ、その「居てるだけ」という行為」も実は親子だからこそできることであったと後々に理解するんですけど、子供の頃はそんな難しいこと分かりませんでした。
父親は父親のペースで子供をもてなしますが、もうそのすれ違いようのひどさはウチと同じでした。
スナックやクラブに連れて行ったり、仕事の用事に着き合わせたり。
子供にとっては、「なんでこんなところに??」ということしかないんですが、この本を読んで痛感しました。
「そうか。おとーちゃんは、こうして「男としての自分」を伝えたかったんやなぁ」と。
「父親としての自分」ではなく「男としての威厳」「ワシはこういう存在なんじゃ」と一個人の自分を子供に示したかったんやろなぁと、ふと、そう思いました。
作品の中で母親が父親に「子供が喜ぶような動物園とか連れていってあげて」という場面があるのですが、じつのところ父親は競馬場に連れて行きます。
皆が皆、一般的に望まれる、一般的描かれる父親になれるわけではないわけで、父親に子供の喜ぶようなところが分からない「男」のまま、父親になる人も居るんですね。ウチの父もそうです。
母親が求める父親らしさ、その逆も然り。それぞれに理想を持つんだろうとは思うけど、子供にとっては実はそんなことどうでもよくて、一番大切なのは一緒に過ごせること。
「●●らしい」なんて後々につける後付けはあっても、子供の時はそんなもの求めてもいないのです。
きっと人は、親になったとき、そういった子供の気持ちというのは忘れてしまうんやろなぁ。
読んでいくうちにウチの家庭と作者の家庭との徹底的な違いは夫婦間に「情」があるということに気が付きました。
とくに作者の母親は、別れる別れるといいながら判を付いてもろた離婚届があるにも関わらず、死ぬまで離婚していないこと。
度々しか会わないけれど、父親と会うときは女らしく身なりを整えること。
そして父親だけに見せる母親じゃない女らしい表情。
そういった例えが度々作品の中で出てきます。
父親もぶっきらぼうながらに母親だけにみせる我儘や甘えなど、別れて暮らしていても想いの先は一つで何かしら一緒に暮らせないお互いの意地みたいなものを節々に感じながら読みました。
それが作者にとって微かながらも確かな家族のつながりを感じていたようにも受け止められます。
2つに割れた茶碗が不細工ながらも繋ぎ合わさって1つの茶碗になってるような、そんな家族に見えました。
ウチは2つに割れた茶碗の片方が、さらに修復不可能なほど粉々に壊れて、もう二度と1つの茶碗に戻ることのない家族でした。
綺麗に割れた片方の破片は、茶碗に戻りたがっていたにも関わらず。
本に書かれた世界みたいにはならず、世の中には、どうにもままならないことがあるのでした。
そやけど、こんな一文に救われました。
“「夫婦にしかわからないことがある」良く聞く言葉だ。それは確かにあるだろう。しかし「夫婦だけがわかってない、自分たちふたりのこと」は子供や他人の方が涼しい眼でよく見えているということもある”
という文章です。
これまた一つの真理で「両親が思っているそれぞれの想いとはかけ離れたところで見る子供からのそれぞれの想い」というものの確かさを作者はこの一文に表してくれました。
ウチの場合、一般的でもないし、きれいなものではないけれど・・・それでもいびつな形でこの2人は惹かれあっていたんやなぁと大人になってからわかることもありました。
父との間に「恋愛感情があった」というのを認めたくない私の母には口が裂けても言えないし、何より認めてもらえませんけど、子供ながらそう感じることは多々あるのも事実。
ここまで、こう書いているとこの本は母親とのことが書かれているにも関わらず、私自身は父親のことをよく思い出しながら読んでいるようにも見えるでしょう。
それもそうです。私と私の母の間には、この物語が入り込む隙などない物語がいくつも紡がれているのですから。
母や母親に対する作者の気持ちは、あまり自分とは重なりません。
むしろ作者に至っては
「こんなエエオカン、なんでそないに苦労させるんや?男やろ?」
と憤ること憤ること(笑)
しかしそう思って我が身を得ってみると私も相当な親不孝者です。
幼少の頃から虚弱体質の登校拒否児、人あたり良く頭もいい長女、友達が多くて運動神経の良い次女たちとは違って何のとりえもない頼りない末っ子。
そのくせ高校は中退、女のくせに料理の世界へ入るのに家出して師匠の家に住み着いての弟子入り修行。いうてる間に兄弟子と結婚して勝浦に嫁いだけれど、7年足らずで離婚して出戻り。
学歴も手に職もないままアルバイトで食いつないで暮らしていたところに今の主人と出会って長い期間半同棲みたいな付き合いを続けてました。
再婚して喫茶店をはじめるという暴挙にもでる始末で、作者みたいに稼げるようになって親を安心させることも未だできず。
母親が生きている間に親孝行ができるとは到底思えません。
そう、母親が生きている間に。
この作品のもっとも佳境である母親との死に向かい合う様は、壮絶です。
こんな苦労して頑張ってきたオカンが、最後そない苦しまなアカンのか?現実は無慈悲でしかない!!!
心が引き裂かれる想いで読みました。
そして死後の作者の心理も然り。しっかり母親の死と向き合っただけに、母親の死は理解できていても、どこかしら何かしら受け入れられないままでいるんだろうなぁと感じました。
父が死んだあの時の私のように。父の死を受け入れるには10年かかりました。
作者が物語の中で一番恐れていたもの。
それは「母親の死」です。
世界の滅亡よりも何よりも現実味があって怖いもの。それが「母親の死」やったんです。
これが一番作者と共通する感情で私は未だその時を迎えていません。いや、迎えたくありません。
かつて作者がそうだったように、そのことを考えると息も出来ないくらい苦しくなって、50を過ぎるというのに大声で泣きたくなるのです。
考えるだけでそんな風になってしまう自分が、その時を迎えたとき、どうなるんやろ?と思うと怖くて怖くてたまりません。
というか母のいない世界なんて考えられないのです。
父の死のとき、あれほど長く苦しく藻掻いたことを思い出すと、またあの時みたいなことがやってくるのかと思うと母より自分が先にこの世からいなくなってしまいたくなります。
誰も、私を、一人残さんといてくれ!
そう跪いて神様に祈りたい気分になります。
物語の中で母親の死を迎えた作者に親戚か誰かに「これでお前も一人前になったな」と言われました。
なんとも妙な励ましやなと思ったんですが、少しわかるような気もします。
つい先日、私自身も馴染みのお好み焼き屋の店主に
「そら、お母さん早よ死んでもらわなあきませんな」
と言われました。
私が母を尊敬していて、母みたいになりたいというような話をしていたときです。
店主が言うた意味がある意味よぉ分かるんですが・・・私はまだそれを受け入れたくない子供です。
人の親になれないのだから、一生母親の子供でいたいんです。
だけど、それも許されないときが必ずきます。
恐らく遠からぬ未来に。
その時、私はどうするのだろう?
その先、私はどう生きていくのだろう?
そんなことを考えさせられる1冊でした。